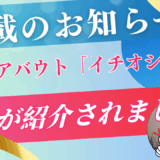日本で2024年12月から施行される「スマートフォン新法」は、EUで1年前に導入された「DMA(デジタル市場法)」と類似しており、AppleやGoogleといった「ゲートキーパー」と呼ばれる巨大IT企業による市場の独占を是正し、自由競争を促進することを目的としています。
本法律は、一見ユーザーにとってメリットがあるように見えますが、EUでの先行事例を見ると、機能制限やセキュリティリスクの増加など、いくつかの懸念点が指摘されています。
主要テーマと重要なポイント
- スマートフォンの独占禁止と市場の開放
- ゲートキーパーへの規制: 本法律は、AppleやGoogleなどのゲートキーパー企業に対し、「スマホ市場を独占しすぎではないか」「新規事業者参入の妨げになっているのではないか」という指摘に基づき、独占的サービスや自社製品間の連携機能の開放を求めています。
- 具体的な規制内容:
- アプリストアの多様化: 現在App Storeからのみダウンロード可能なiPhone/iPadアプリを、App Store以外のプラットフォームからもダウンロード可能にするよう要求。
- 課金システムの選択肢拡大: 現在Appleを介して行われるアプリ内課金(通称「Apple税」30%)に対し、Appleを通さずアプリ開発者に直接課金できる選択肢の提供を求める。
- ブラウザの選択の自由: 初期設定でSafariのみが搭載されている現状を改め、スマートフォンセットアップ時にユーザーが自由にブラウザを選択できるようにする。
- 連携機能の開放: Apple製品間のシームレスな連携機能(例:AirPods、iPhone/iPad/Mac間の連携)を、他社のデバイスでも利用できるように開放するよう求める。
- EUでの先行事例とその影響
- 機能制限の発生: EUでのDMA施行後、Appleデバイスから便利な機能が次々と規制され、使用できなくなっています。これは法律が「機能を解放しなさい」と定めているにもかかわらず、実際には機能が制限される方向に進んでいると指摘されています。
- 具体的な機能制限の例:
- ミラーリング機能: MacBook上でiPhoneを遠隔操作する機能が、セキュリティ上の理由からEUでは使用できなくなりました。Appleは「安全性を考慮すると他社製品への開放は困難」とし、結果としてEU限定で機能自体を無効化したとされています。
- その他: マップ機能の一部、ライブアクティビティ機能、Apple Intelligenceの一部機能などもEUのみで利用できなくなっています。
- ユーザーの不満: これらの機能制限により、EUのユーザーからは批判の声が圧倒的に多く上がっています。
- 日本への影響とEUとの相違点
- 日本も同様の道を辿る可能性: 日本のスマートフォン新法はEUのDMAを後追いする形であるため、同様の機能制限が日本でも発生する可能性が懸念されています。
- 日本版の「セキュリティ例外」: 日本の法律には「セキュリティ例外」という文言が含まれており、「セキュリティやプライバシーの保護上懸念が残る機能については規制対象から除外できる」と規定されています。これはEUにはない特例であり、Apple側がセキュリティ上の理由を主張することで、一部の機能は開放を免れる可能性があるとされています。
- 定義の抽象性: しかし一方で、日本のガイドラインにおける禁止される行為の定義が抽象的であるため、Apple側からすれば何が良くて何が悪いかの判断が難しく、「後出しジャンケン」的に規制されることを避けるため、積極的に機能を制限してくる可能性も指摘されています。
- ユーザーへの潜在的なデメリット
- サポート品質の低下: アプリ開発者への直接課金が選択肢として増えることで、料金が安くなる可能性があります。しかし、Appleを介さない場合、Appleの提供する手厚いサポート(例:トラブル時の返金対応、サブスクリプションの簡単な解約)が受けられなくなる可能性があります。悪質な業者との直接取引では、返金や解約が困難になるリスクが考えられます。
- Apple安全神話の崩壊とセキュリティリスクの増加:
- App Storeの審査: AppleはこれまでApp Store上のすべてのアプリを厳しく審査し、マルウェアやウイルスの排除に努めてきたため、「Apple安全神話」と呼ばれる高いセキュリティが保たれていました。Kasperskyの報告によると、2023年にはGoogle Playのアプリから6億件以上のマルウェアがダウンロードされたのに対し、App Storeからはごく少数しか確認されていません。
- サイドローディングの危険性: 12月以降はApp Store以外の場所からもアプリをダウンロードできるようになるため、マルウェアが混入したアプリを意図せずダウンロードしてしまうリスクが高まります。
- 危険なアプリの出現: EUではAppleが規制していたポルノ系アプリが登場しており、日本では違法ギャンブルアプリなどが出現する可能性も指摘されています。
- ITリテラシーの重要性: これまでの「超安全な環境」が「普通」になるだけで、ITリテラシーが高いユーザーは引き続き安全に利用できますが、ITリテラシーが低いユーザーや情報に興味がないユーザーが被害に遭う可能性が高まるため、ユーザー側の注意喚起とリテラシー向上が重要となります。
- 法改正の背景と今後の展望
- 世界的な動向: スマートフォン新法のような独占禁止を目的とした動きは、日本とEUだけでなく、イギリス(2024年法案通過予定)、韓国、トルコ、ブラジル、メキシコ、オーストラリア、南アフリカなど、世界の多くの国で同様の法律が立案中です。
- 評価の不確実性: EUでのDMAはまだ始まって1年であり、自由競争活性化の目的が達成されるかはまだ不明確です。今後の結果が良い方向に向かうのか、悪い方向に向かうのかは、現時点では誰にも予測できません。
結論
日本のスマートフォン新法は、市場の公正な競争を促進するという大きな目的を掲げていますが、EUの先行事例から、ユーザーの利便性の低下やセキュリティリスクの増加といった潜在的なデメリットも浮上しています。特に、ユーザーは今後、アプリのダウンロード元や課金方法の選択において、より高いITリテラシーと注意が求められることになります。この法律が最終的に日本市場とユーザーにとってどのような結果をもたらすかは、今後のAppleの対応や世論の動向によって大きく左右されるでしょう。
新法で「選べる自由」は増えますが、「安全」や「便利さ」が減るかもしれません。
特にシニア世代は「どこからアプリを入れるか」「支払い方法は安全か」に気をつけることが大切です。
スマホはますます便利になりますが、同時に「自分で守る意識」も必要になってきます。